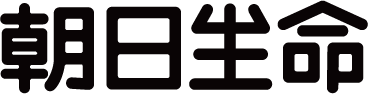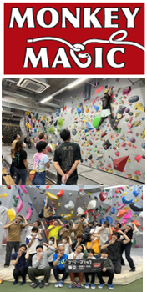受賞事例をより深い情報で解剖し、デザインアプローチによる開発手法と評価手法を研究する。本研究の成果を多くの企業が今後の開発に活用し、効率的なビジネス化の支援となることを目的としています。
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
(愛称:あすのはね)

| 基準価額(円) | |
|---|---|
| 前日比(円) | |
| 純資産総額(百万円) |
| 分配金実績 | ||
|---|---|---|
| 決算期 |
分配金(円)
基準価額:分配落(円)
|
|
| 設定来分配金累計(円・2000年9月28日設定) | |
|---|---|
| 決算期 |
分配金(円)
基準価額:分配落(円)
|
チャート
※基準価額は1万口あたり、分配金は1万口あたり税引前の金額です。
※基準価額(税引前分配金再投資ベース)は信託報酬控除後であり、税引前分配金を再投資したものとして計算しています。
換金時の費用、手数料等は考慮しておりません。
※基準価額は信託報酬控除後です。
※実績数値は過去のものであり、将来の運用成果、分配金の支払いおよびその金額を示唆あるいは保証するものではありません。
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率(%) |
※期間別騰落率は税引前分配金を再投資したものと仮定して計算しています。換金時の費用、手数料等は考慮しておりません。
- コラム・レポート
- 22期寄付先情報
- 23期寄付先情報
- 関連ページ
-
2024年4月9日
-
2024年3月11日
-
2024年2月8日
-
2024年1月12日
- 第22期寄付先に関する活動報告 -
第22期寄付先に関する活動報告
第22期(決算日2022年9月20日)は次の7団体に寄付を行いました。
寄付先団体からの活動報告は以下のとおりです。
アフターケア相談所 ゆずりは(社会福祉法人 子供の家)
安心と楽しいを一緒に育む
今年度のあすのはねのご寄付は、就労支援の一環として開催している「ゆずりは工房」でのジャム作りに活用させていただきました。ゆずりはの相談者の中には、虐待被害者やヤングケアラー状態でなんとか生きてきた多くの若者がいます。当初の相談では、生活困窮やネグレクト等の虐待被害であっても、支援を進めて行く中で、幼い頃からヤングケアラー状態であったことが明らかになるケースがあります。ヤングケアラーであった人は、相談機関にたどり着けても、安心な心の状態を取り戻すことは容易ではありません。長きにわたって、子どもとしてのびのびと安心して生きられなかった苦しみや辛さなどを言葉にして誰かと分かち合うこと、そして、自分が「生きていても良い」と思える大きな一助となるのが、「働ける」「誰かの役に立てる」ことでもあります。「ゆずりは工房」は、そのような境遇にある人たちに、お互いの苦しみや悲しみを分かち合う場所を提供しています。今年度は、年間43回開催し、延べ288名が参加しました。
認定特定非営利活動法人 キッズドア
すべての子どもたちが夢や希望を持てる社会の実現を目指しています
第22期のご寄付は、全国の大学進学を目指す高校生のためのオンライン学習会での支援ツールに活用させていただきました。高校卒業後の進路において大学進学率が向上している中、困窮世帯の高校生は予備校に通うことも難しい状況です。現在の大学進学では学力はもちろんですが、情報と戦略が必要不可欠です。複雑化する入試制度を理解しどのように準備していくかは、予備校に通っている子たちとの間で大きな格差となります。キッズドアでは全国の困窮世帯の大学進学を目指している高校生へ向けて募集を行い、オンラインによる学習支援で高校生に受験まで伴走しています。現在約100人の登録生徒がおり、全国各所からオンラインで繋がり大学進学に向けての取り組みをしています。いただいたご寄付で導入したシステムは、生徒の学習状況や志望大学までの目標達成度合いを可視化できるツールです。このツールを利用して受験戦略を立てることもでき適切な指導ができるようになりました。温かいご支援に感謝いたします。
社会福祉法人 子どもの虐待防止センター
子どもの虐待防止に取り組む専門の民間相談機関
日頃より温かいご支援を賜りましてありがとうございます。
今期のご支援は、活動の柱である相談事業に参加するボランティアの活動に活用させて頂きました。ホームページのリニューアルの効果もあり、コロナ禍を経て、「子どもを叩いてしまった」「子どもがかわいく思えない」などをキーワードに、初めて相談を利用される方も増加傾向にあり、昨年度の相談件数は2,625件となりました。また母親グループ「MCG(母と子の関係を考える会)」にも新たな問い合わせが入っています。当法人の電話相談やMCGなどの事業は、研修を受けたボランティアが臨床心理士や行政経験のある専門職のサポートを受けながら対応に当たっています。各事業に従事するために行う研修にもご支援を活用し、延べ500名が参加することができました。
皆様のご支援の下、これからも相談を寄せて下さるお一人お一人に寄り添う丁寧な活動に努めて参ります。ありがとうございました。
認定特定非営利活動法人 自然環境復元協会
自然環境の復元と、ヒトが心豊かに暮らせる地域社会の創造
ご支援いただいたご寄付は、レンジャーズプロジェクトの活動の維持・促進のために役立たせていただきました。レンジャーズリーダー研修会の開催などリーダーの育成・登用、また、ホームページやSNSによる、活動地やボランティアの募集といった活動拡大のための広報活動に活用いたしました。安全管理や活動体制の強化を図り、参加機会の増加や、ボランティア登録者数の増員に繋げることができました。
今年度は、新規の活動場所を2か所追加し、年間で423名のボランティアの方々の参加を得て、東京・埼玉・神奈川・大阪の各地で計43回の活動を行うことができました。また、ボランティア登録者数も4,733名にまで増やすことができました。
今後も、多様な生き物と共に暮らす社会の実現に向け、「身近な自然環境を復元すること。」「自然体験を通した豊かな感性と人間力溢れるヒトが育つ場を提供すること。」を目指し、活動に邁進いたします。皆様のご協力とご支援に法人一同心より感謝申し上げます。
特定非営利活動法人 樹木・環境ネットワーク協会[愛称:聚(しゅう)]
自然とともに生きる社会づくりの推進
2022年度においては、コロナ禍以前の保全活動をほぼ再開し、活動も活発になりました。反面、雑木林ではナラ枯れという突然樹木が枯死する現象が多発し、その対応に追われた年でもありました。枯死自体は社会的にも大きな問題となりましたが、私どもとしては、森の再生の一端ととらえ、整備・保全活動を進めています。また、自然観察会や子どもの自然体験活動も再開し季節ごとに実施することができました。
グリーンセイバー資格検定では、CBT試験を採用し、全国的に受験が可能となりました。受験者としては思うような結果を得ることが出来ず、CBT方式との関係性、広報の課題等を分析し、今後の対策を検討中です。
人材育成の一環で行っている「里山林塾」では、里山の整備活動を学ぶだけでなく、利活用や楽しみを実現する活動としても展開をしています。養蜂や休耕田の開墾など、興味のある分野でお互いに学びながら里山を活かし、自然を豊かにしていくものとして期待しています。
認定特定非営利活動法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ
ママが元気になれば子どももしあわせに!
シングルマザーが子どもといっしょに生き生き楽しく生きられるように、ママを勇気づけ、社会で活躍できる支援を行っています
第22期のご寄付は相談業務に活用させていただきました。しんぐるまざあず・ふぉーらむの2022年度の相談受付件数は、メール946件、電話925件でした。コロナ禍で相談が急増した2020年度からは4割減ですが、2021年度からはほぼ横ばいで、コロナ禍以前と比べると2倍以上に増加したままの状態です。
コロナ禍による離職や失職などで経済的困窮に陥ったひとり親が多い中、昨春以降の物価高がさらに生活の厳しさに拍車をかけました。当団体のひとり親家庭調査で「主食の米が買えないことがあった」が56%など、衣食住を欠く状況が広がっています。子どもの不登校や障がい、親の介護など、家族の事情を抱える人も少なくありません。相談者の気持ちを受容し孤立をやわらげつつ、当団体の食料支援につなげたり、地元の支援団体や社会福祉協議会などにつなげたりと、「一人も取りこぼさない」ことに心を砕きました。LINEでの相談も2年目に入り、若いママたちとの連絡手段として有効に活用しています。
特定非営利活動法人 モンキーマジック
障害者クライミング普及活動を通じて、多様性を認め合えるユニバーサルな社会の実現を目指しています
第22期のご寄付は、弊会の障害者クライミング普及活動のノウハウを日本全国に共有し、クライミングを通じた地域コミュニティ創造のため、日本各地の有志によるクライミングサークルの支援に充てさせていただきました。
クライミングサークルを「全国交流型クライミングイベント」と題して、各地で主催者と教育・医療関係者を繋ぎ、イベントの基盤づくりを行いました。
現在、北は北海道から南は沖縄まで、全国18地域(札幌・函館・富山・山梨・愛知・京都・大阪・島根・岡山・広島・徳島・高知・福岡・熊本・鳥取・北九州・宮崎・沖縄)に拡大することができました。
今後も外出機会の少ない障害当事者に向けて、スポーツの選択肢を広げ、社会参加、健康寿命の延伸に寄与します。そして障害者と健常者の相互理解を深め、多様性を認め合えるユニバーサルな社会の実現を目指します。
全国47都道府県での展開を目指して、今後も人々の可能性を大きく広げることを目的として活動に邁進いたします。
- 本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社といいます)が、寄付先団体の開示を目的として作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。
- 第23期寄付について -
第23期寄付先のご紹介
第23期(決算日2023年9月20日)は信託報酬の中から総額4,222,446円(日々の信託財産の純資産総額に年0.1~0.2%の率を乗じて得た金額)を、以下の7団体に寄付しました。
アフターケア相談所 ゆずりは (社会福祉法人 子供の家)
安心と楽しいを一緒に育む
「アフターケア相談所ゆずりは」は、児童養護施設や里親のもとを巣立った人や、虐待や貧困等の理由から親や家族を頼れず孤立している人たちへの支援を行う相談所です。住まいや、仕事、病気、様々な困りごとの相談を受け、生活保護の申請の補助、病院や不動産屋への同行等も行っており、ひとりひとりの相談者に寄り添っていくことを大切にしています。個別の相談対応の他に、「ゆずりは」の場所を拠点に、気軽に集えるサロンや、働く場として「ゆずりは工房」でのジャムづくり、高卒認定資格取得のための無料学習会、みんなでごはんの会、子どもへの不適切な行為をやめたい親を対象とした「MY TREEペアレンツ・プログラム」なども実施しています。「自分なんか生まれてこなければよかった」「生きている価値がない」と苦しみを抱えているひとたちが、出会い、つながり、安心できる時間を積み重ねていくことで、自分の暮らしを楽しみ、大切にできる気持ちが芽生え育まれていくことを大切にして活動しています。
《SDGs目標》
1.貧困をなくそう
3.すべての人に健康と福祉を
特定非営利活動法人 OWS (The Oceanic Wildlife Society)
海を通じて、自然との共存を学び、確立します
OWSは1998年に設立した海の環境NPO法人です。海をとりまく自然とそこにすむ生き物を通して、「自然に親しむ・自然を学ぶ・自然の大切さを伝える」活動を推進しています。
現在、主に次の4プロジェクトに取り組み、さまざまな連携や協働を創出しています。
◆海の子プロジェクト:海離れ、自然離れが著しい現在、自然体験学習を通して子どもたちに海の自然や生き物とのふれあいの機会を創出しています。これまで3,200名以上の子どもたちが参加しています。
◆サンゴ調査プロジェクト:研究者との連携による、温暖化の影響評価のためのサンゴおよび魚類のモニタリング調査等を全国10以上の海域で実施しています。
◆海洋ごみプロジェクト:学校等への教材提供、講演、写真資料展、ごみ回収活動等、毎年5,000人以上を対象目標とする海洋ごみ削減の普及啓発を実施しています。
◆干潟保全プロジェクト:研究者、地元住民等多様な主体と連携・協力して行う希少干潟環境の保全活動です。紀伊半島、三浦半島を中心に黒潮流域の各干潟での調査も実施しています。
《SDGs目標》
14.海の豊かさを守ろう
認定特定非営利活動法人 キッズドア
すべての子どもたちが夢や希望を持てる社会の実現を目指しています
認定NPO法人キッズドアでは、2007年の設立以来「日本の子どもの貧困」に取り組んでいます。生まれてきた環境や災害などによって、子どもたちの将来の夢や希望に不平等が生じる社会はおかしい、困難な状況にある子どもたちにもフェアなチャンスのある社会を作りたいという想いで活動しています。
キッズドアが関わる子どもたちは、ご家庭の収入が厳しいため十分な教育が受けられず、進学や就職も不利となり、子どもたちが親世代になった時にもこの状況は連鎖してしまいます。この「連鎖」を断ち切るために、東京、宮城を中心に無料の学習支援や、子どもたちが毎日過ごせて食事の提供も行う居場所の運営を行っています。2022年度は、国内84拠点で学習支援や居場所を提供し、2,030人の小学生から高校生世代のお子さんに通っていただきました。本事業の学習支援には1,384人もの市民ボランティアの皆さんに関わっていただき、継続的に活動することができています。
《SDGs目標》
1.貧困をなくそう
4.質の高い教育をみんなに
社会福祉法人 子どもの虐待防止センター
子どもの虐待防止に取り組む専門の民間相談機関
社会福祉法人子どもの虐待防止センター(CCAP)は、1991年から主に家庭内で起こる子どもの虐待防止のために活動する民間の団体です(社会福祉法人認可は1997年)。当法人は、設立時より子どもを虐待から守るためには家族へのサポートが重要であることを活動の柱に据え、子育てに悩む親を対象とした電話相談や母親グループ「MCG(母と子の関係を考える会)」のほか、当法人の2つの独自プログラムである「CCAP版 親と子の関係を育てるペアレンティングプログラム®」と「アタッチメント形成のための心理療法プログラム」を行っています。また里親・養親支援事業、研修とともに、公益事業として児童精神科を中心としたクリニックを開院しました。
虐待は子どもの人生に深い影を落とします。親もまた困難を抱えて苦しんでいることも多く、親を責めるだけでは問題は解決しません。私たちは民間の相談窓口として多くの方にご利用頂くとともに、活動を通じて温かいサポートの必要性を社会に発信していきます。
《SDGs目標》
1.貧困をなくそう
3.すべての人に健康と福祉を
10.人や国の不平等をなくそう
16.平和と公正をすべての人に
認定特定非営利活動法人 自然環境復元協会
自然環境の復元と、ヒトが心豊かに暮らせる地域社会の創造
多様な生き物と共に暮らす社会を目指し、「身近な自然環境を復元すること。」「自然体験を通した豊かな感性と人間力溢れるヒトが育つ場を提供すること。」を使命に、日本国内にて主に3つの事業を行っています。
◆ふるさと未来創造プロジェクト
多くの農村が過疎化などの問題を抱えています。都市と農村を結びつけ協働することで、農山漁村の生態系を豊かにすることや、地域の問題解決と活性化を目指しています。
◆環境再生医制度
環境再生医の資格制度を運営しています。「自然環境」と「自然とヒトの関係」の再生を目指すSDGs視点の環境人材を、育成・支援しています。
◆レンジャーズプロジェクト
若手のボランティア希望者が地域の環境保全団体へお手伝いに行く環境保全ボランティアです。ボランティア希望者が環境活動を始めるきっかけを創出し、高齢化や人手不足などで困っている環境保全団体の課題解決を目指します。
《SDGs目標》
2.飢餓をゼロに
3.すべての人に健康と福祉を
4.質の高い教育をみんなに
11.住み続けられるまちづくりを
12.つくる責任・つかう責任
13.気候変動に具体的な対策を
15.陸の豊かさも守ろう
17.パートナーシップで目標を達成しよう
特定非営利活動法人 樹木・環境ネットワーク協会[愛称:聚(しゅう)]
自然とともに生きる社会づくりの推進
持続可能な社会を目指し、人と自然の調和のための活動を行っているNPO団体です。「森を守る」、特に里山を通じて自然との関わりを取り戻し、そこで活動する「人を育てる」活動も行っています。そして、社会へつなげるための「森と人を繋ぐ」をテーマに、企業や行政と連携し、子どもたちの環境教育的活動や森づくり活動を推進・普及しています。
「森を守る」・・・全国で定例的な整備・保全活動を進めています。里山をモデルに、人が自然に手を入れ、利用することでより豊かな自然環境を維持することができるような活動を目指しています。
「人を育てる」・・・グリーンセイバー資格検定を軸に、セミナーや研修会等、環境活動を推進する人材の育成を行っています。
「森と人を繋ぐ」・・・社会への普及啓発を目的に、観察会や自然体験活動の企画運営をしています。行政と連携した緑地の保全活動や、企業の社会貢献の提案や活動の受入れなども行っています。
《SDGs目標》
4.質の高い教育をみんなに
8.働きがいも経済成長も
11.住み続けられるまちづくりを
13.気候変動に具体的な対策を
14.海の豊かさを守ろう
15.陸の豊かさも守ろう
17.パートナーシップで目標を達成しよう
特定非営利活動法人 モンキーマジック
障害者クライミング普及活動を通じて、多様性を認め合えるユニバーサルな社会の実現を目指しています
「見えない壁だって、越えられる。」をコンセプトに、国内で18年以上にわたり、障害のある児童生徒・大人を対象としたクライミングスクール、そして障害のある方もない方も共に楽しめる交流型クライミングイベントの定期的な企画運営、講演会や体験会を実施しています。
クライミングは障害の有無に関係なく、同じ場所で同じルールで楽しむことができます。健常者と障害者が「助ける・助けられる」の関係ではなく、同じクライミング仲間として関わり、互いに壁を取り払い、理解しあうことで、多様性を認め合える価値ある機会となります。
障害、年齢、性別、文化などの違いに関わりなく、それぞれの人が社会の一員として支え合う中で、安心して暮らし、一人一人が自分らしく生き、持てる力を発揮して元気に暮らすことのできる社会を目指しています。
《SDGs目標》
3.すべての人に健康と福祉を
10.人や国の不平等をなくそう
注:上記7団体は、第23期計算期間にかかる金額を寄付をさせていただいた団体であり、第24期計算期間以降については、上記の団体に寄付を行うとは限りません。
※写真は、当社代表取締役社長の藤岡から各団体に目録を贈呈後、記念撮影をしたものです。
■表記ファンドにかかる寄付金額および寄付先等については、運用報告書等において公表しています。
- 本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社といいます)が、寄付先団体の開示を目的として作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。
-
2024年4月8日
-
2024年4月1日
-
2024年3月25日
投資信託ご購入の注意点
- 本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社といいます)が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。
- 当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
- 本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。
- 本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
- 本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。
- ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
- 当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。